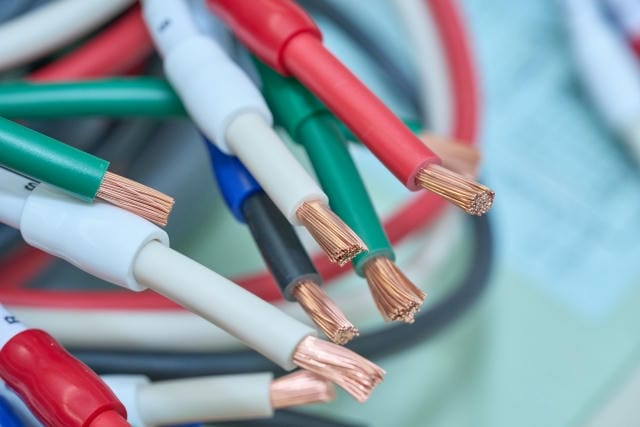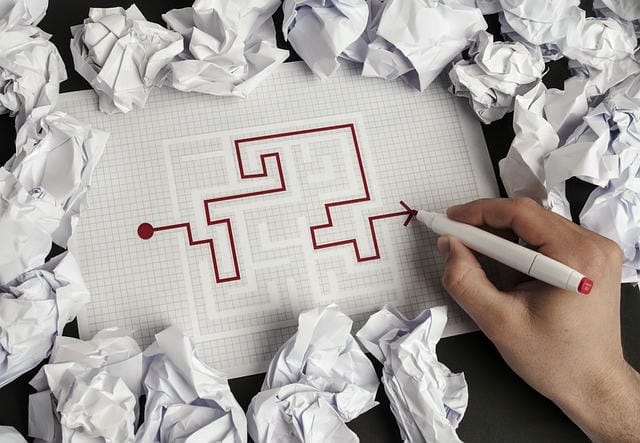
業務用の端末やサーバーを守るうえで、これまで多くの組織がウイルス対策ソフトを導入してきたが、攻撃手法の多様化や高度化によって従来型の対策だけでは十分な保護が困難になっている。そうした状況の中で注目されているのが、EDRである。この技術は、不正アクセスやマルウェア感染などのサイバー攻撃からコンピューターやサーバーを守る新しい防御手法として広がりを見せている。 EDRとは、「端末検知および対応」の略称であり、主に社内ネットワークに接続する端末の挙動を常時監視し、不審な動作があれば早期に検知、調査、対処まで自動的もしくは遠隔操作により行う仕組みを意味する。これまで主流だったウイルス対策ソフトは既知のマルウェアや不正プログラムをパターンファイルに基づいて排除する手法が多かった。
それに対してEDRは、未知の攻撃や内部不正といったパターンファイルでは捉えきれない異常挙動も検知できる点に特徴がある。 すべての端末やサーバーの動作ログを幅広く取得し、それを専用のシステムで分析することで、ネットワーク内で発生した異常の兆候をいち早く把握できる。例えば、新規の不審なプロセスが起動した、利用者が夜間にもかかわらず大量のデータを外部に転送している、権限のない操作が繰り返されているといった挙動は、その時点で速やかに警告が発される。 これら調査や対応作業が自動化されていたり、セキュリティ部門の担当者が遠隔から指示を出し素早く封じ込めるアクションが実施できることもEDRの大きな特長のひとつだ。たとえば、実際に怪しい挙動が検知された場合は、その端末やサーバーのネットワーク接続を一時的に遮断したり、マルウェア感染が疑われるファイルの隔離といった具体的な防御策を瞬時に講じることができる。
こうすることで、被害の範囲拡大や重要な情報の漏洩を未然に防ぐことにつながる。 さらにEDRは、ネットワーク内でどんな活動が行われていたのか、過去のログを遡って調査できる点でも優れている。もし組織内の重要な情報が不正に持ち出されてしまった場合でも、いつ、どの端末から、どんな操作がなされたのかを詳細に追跡することが可能だ。このように、事後対応や原因究明の際にも大きな助けとなっている。サーバー自体に簡単には認識できない攻撃や、内部からの持ち出しによる情報漏洩などは、往々にして一連の利用履歴の記録を調査しなければ把握が難しいものである。
EDRの普及によって、目に見えない不正行為の解明が飛躍的に効率化されたと言える。 一方で、EDR導入にはネットワークやシステム全体への影響も考慮すべき要素がある。たとえば、多数の端末・サーバーの監視を同時に行うにあたり、取得する動作履歴や分析データが膨大となるため、そのためのストレージや通信帯域の確保、サーバーリソースへの負荷、適切な運用体制の構築が必須となる。監視や解析を担うサーバーの硬直や遅延の発生は、全体のセキュリティ監視網の品質を下げてしまうことにつながるため、事前に十分な設計と検証を行うことが大切だ。 また、EDRは単体では万全な防御策とはならないという点にも注意が必要である。
端末やサーバーでの不審な挙動を正しく検知・防御することもさることながら、ファイアウォール、侵入検知システム、メールゲートウェイなど、他のセキュリティ対策との組み合わせが強固な防御体制を構築するために欠かせない。加えて、管理を担当する情報システム部門やセキュリティ担当者の知識や体制強化、ユーザーへの継続的な教育・訓練の実施も含めて、組織全体としての広範な取り組みが求められる。 端末の多様化、クラウド環境へのシステム移行、テレワークを始めとした社外からのアクセス増大など、組織を取り巻くIT環境は大きな変化を遂げている。これに伴い、端末やサーバーから生じる情報セキュリティのリスクも広がっている現代において、EDRを活用した「早期発見・迅速対応」は、有効で不可欠な対策手法の一つと言える。従来の境界型防御では捉えきれなかった高度な攻撃にも幅広く備えるため、多層的な防御策の第一線を担う存在として、EDRの活用が強く推奨されている。
今後も情報システムの複雑化や攻撃手段の進化に伴い、EDRを核としながらネットワークやサーバー全体を守る高度な監視・防御技術はますます発展していくことが予想されている。それぞれの組織にあった適切な導入・運用を進めることによって、情報漏洩や被害のリスクを大幅に減らすことが可能になるのは間違いない。導入においては、自社のネットワーク構成やセキュリティポリシー、運用リソースと照らし合わせ、最も効果的なシステム設計を目指すことが肝要だと言える。業務用端末やサーバーのセキュリティ対策として従来主流だったウイルス対策ソフトは、攻撃手法の高度化により十分な対策が難しくなっている。そこで注目されているのがEDR(端末検知および対応)であり、端末やサーバーの挙動を常時監視し、不審な動きを自動的または遠隔で検知・調査・対応できる点が特徴だ。
EDRは未知の攻撃や内部不正も検知できるため、パターンファイルに依存するウイルス対策ソフトでは見落としがちな異常も早期発見が可能となる。具体的には、夜間の大容量データ移動や権限外操作などの不審な挙動を即座に検知し、端末の隔離やファイルの隔離など迅速な防御措置を取ることができる。また過去の操作ログに基づく追跡調査も容易となり、事後の原因究明や被害範囲の特定にも貢献する。一方で、EDR運用には大量ログの保存や解析に伴うサーバー負荷、ネットワーク帯域確保、監視体制強化などの課題も存在する。また、単独でのEDR導入では十分な防御ができないため、ファイアウォールや他のセキュリティ対策と組み合わせて多層防御を構築する必要がある。
情報システム部門やユーザーへの教育も含めた総合的な取り組みが求められる。IT環境の変化に適応し、高度化する脅威に対抗するうえで、EDRを活用した早期発見・迅速対応は極めて有効な対策と言える。今後もEDRを核とする防御技術の発展が期待され、組織ごとに最適な導入運用を進めることが重要である。EDRとはのことならこちら