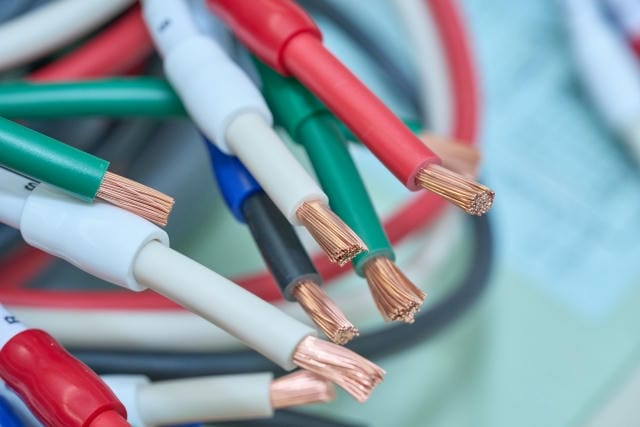さまざまなサイバー攻撃が増加するにつれ、企業や組織の情報システムでは高度なセキュリティ対策が求められるようになっている。その中でもEDRが注目されているのは、従来の境界型防御を超えて、個々の端末やサーバー内で発生した異常な挙動を詳細に監視・検知し、迅速に対応できる点が大きい。従来用いられてきたセキュリティ対策では、主にネットワークの出入り口やファイアウォール、ウイルス対策ソフトによって不正侵入やマルウェアの拡散を防ぐことが試みられてきた。しかし、標的型攻撃や内部犯行といった近年進化するサイバー攻撃の手口に対し、このような従来型の対策だけでは対処が困難になってきている。EDRでは、まず端末やサーバー上のプロセスやメモリ、ファイル操作、通信といった詳細な動作ログを収集する。
このログ情報はリアルタイムで分析され、既知または未知の脅威につながる兆候を検知する仕組みとなっている。通常では考えにくいプログラムの起動や、不審なファイルの書き換え、権限の昇格、またネットワーク上での異常な送受信を捕捉することで、攻撃を早期に発見できる。更に、EDRによっては分析されたデータが一元的にクラウドや専用サーバーに蓄積され、その場で自動分析や専門家による調査が可能となる。これにより攻撃の全貌を迅速につかみ出し、被害拡大を未然に防ぐ対応へと繋げられる。特筆すべきは、EDRが感染・侵害後の「事後対応」にも力を発揮する点である。
システムに対する攻撃の模様を時系列で追跡できるため、侵入経路やその後の攻撃者の動作、そして最終的にどの情報・データが影響を受けたのかを正確に突き止められる。これによりインシデント発生後の迅速な封じ込めや、原因究明、安全性の担保といった一連の対策がロスなく進められる。端末やサーバー単体ではもちろん、全社的に導入の規模が拡大することで、横断的にネットワーク全体の脅威情報を集約し、連動対応を取ることができる点も、EDRの大きな特徴となっている。また、EDRはネットワーク機器やサーバー群と連携することで、高度な相関分析が可能となる。たとえば、ある端末で発見された攻撃の痕跡が、組織内他の端末やサーバーにも類似していないか、設定ファイルやネットワークログを横断的に確認できる。
場合によっては、被害が及びそうな範囲をAIやパターン分析によって迅速に推定し、該当範囲のシステムを隔離状態へと自動移行させることも可能だ。このようにして、端末上に導入されたエージェントがネットワークを通じて中央管理サーバーと連携する形をとり、全体制御やインシデント対応を一元化することで、より素早い防御体制を実現している。一方、EDR導入にあたっては注意点もある。例えば、膨大な量のログデータを常時収集・分析するため、サーバーやネットワーク負荷が増加する。組織の規模や運用体制に応じて、適切なリソース管理やチューニングが必要となる。
また、EDRが示す検知アラートの中には、通常業務の範囲内の動作も含まれ、誤検知や対応過多のリスクがある。そのため、現場の情報システム担当者には、検知内容の精査やアラート管理といった業務の負担増も想定されるため、事前の運用体制強化と共に、組織内のセキュリティ教育や手順整備も不可欠となる。加えて、EDRの機能を最大限に活用するためには、ユーザーの行動記録や重要なデータが一括管理される必要から、プライバシーや個人情報の管理にも配慮が求められる。これらのコンプライアンスや内部ガイドライン作成など、多角的な体制整備が重要となる。クラウド化やリモートワークの広がりとともに、ネットワーク外でも端末やサーバーが自在に接続される時代となった。
そのため、単なる拠点の境界防御以上のことを求める現場が多い。EDRはそうした環境下でもそれぞれの端末やサーバーを個別に監視・制御可能とし、多様な働き方・構成にも柔軟に適応可能なツールである。攻撃が実際に成立してしまってから、被害が大きく拡大する前にいかに発見し、情報流出やシステム停止などの深刻な事案に進展させないか。EDRはこの「攻撃を早期発見し封じ込める」という確実な目的意識のもとに進化を続けている。現実の運用においては、ウイルス対策ソフトとEDR、ファイアウォール、それにネットワーク監視といった複数層のセキュリティを組み合わせるのが理想的とされる。
こうした多層防御のなかでもEDRは、個々のサーバーや端末内部で何が起きているのかをきめ細やかに把握し、かつ全体管理サーバーに集約された情報資産をもとに、組織全体での横断的なセキュリティ運用をサポートするため、現代のシステム管理にとって欠かせない位置付けとなっている。今後もネットワーク、サーバー、端末といったあらゆる領域において、EDRによる監視と自動化、分析技術は、一層の発展が期待される。近年、サイバー攻撃が巧妙化・多様化する中で、従来のファイアウォールやウイルス対策ソフトといった境界型防御だけでは十分なセキュリティ確保が困難となっている。これに対し、EDRは端末やサーバーのプロセス・ファイル操作・通信などの詳細な動作ログをリアルタイムに監視・分析し、通常とは異なる挙動を検知することで、未知の脅威や内部犯行も早期に発見・対応できる強みがある。また、インシデント発生時には攻撃の全貌を時系列で把握し、影響範囲の特定や封じ込め、原因究明を迅速に行うことが可能となる。
EDRはクラウドや専用サーバーと連携し、全社横断的な脅威の把握や自動分析による防御体制の効率化も実現する。一方で、膨大なログ分析によるシステム負荷やアラート対応の負担増、誤検知のリスク、プライバシー保護やコンプライアンス面での課題もあるため、導入には運用体制の強化や社内教育、ガイドライン整備が不可欠である。クラウドやリモートワークの普及により、端末がネットワーク境界を越えて利用される現代において、EDRは多様な働き方や構成に柔軟に対応しつつ、攻撃の早期発見と封じ込めを重視する新たな要となっている。今後は従来型セキュリティと組み合わせた多層防御の中核として、EDRの技術と運用はますます重要性を高めていくだろう。